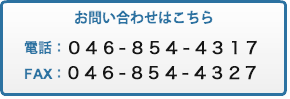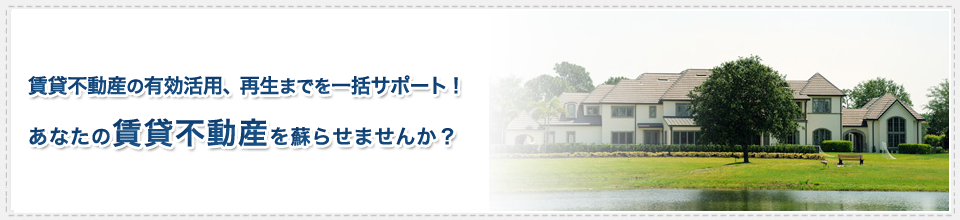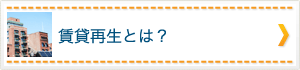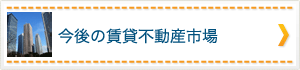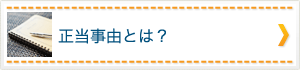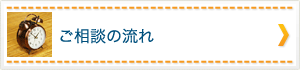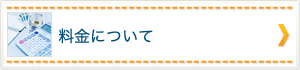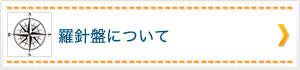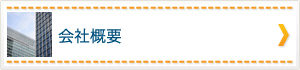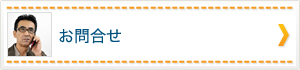「不動産格差社会」の進展
先週22日、ECB(欧州中央銀行)は、量的緩和措置を導入することを決定致しました。
この様な経済情勢の中で、日本の不動産市場には外国人の買が多く入っていると言われており、商業地を中心に値上がりが続いております。しかし、平成元年(1989年)の頃の、所謂バブル期と現状の不動産を比較した場合、不動産の地価水準は、バブル期は、全国的に地価上昇が見られましたが、現在は、将来の人口動向を見据えたものとなっており、都会と地方との格差から都会内での格差となって現れております。東京や横浜と言った大都会でも、その中で不動産格差がついているのが現状ではないでしょうか。例えば、横浜市では、将来、人口増加が予想される北部の地域では、地価が強含みに推移しているのにも関わらず、人口減少が予想される南部では、弱含みに推移しております。(平成26年基準地価)
更に、重要なことは、最寄り駅から都心のターミナル駅までの距離及び最寄り駅から対象不動産までの距離によって、今まで以上の大きな差が見られることです。このことは、既に不動産は、将来の需給を考慮して、格差社会に突入したのではないでしょうか。
従来から、賃貸不動産マーケットにおいては、一部の特殊な要因を除き、駅からの距離によって、その空室率が比例して上がっており、当社の調査では、徒歩10分を超えた賃貸物件の空室率は、極端に高くなっております。即ち、東京や横浜と言った大都市の中でも、確実に不動産の格差は広がっており、今後の少子高齢化の進展によって更なる格差となって現れると、当社では考えております。
今後、賃貸不動産の格差は、所謂自己使用の住宅用地よりは大きくなることが予想されます。現状で、賃貸不動産を所有されている方は、常に、ご自分の賃貸不動産を客観的に見直しながら、今後の賃貸経営のあり方を再考されることを是非お勧め致します。
当社では、現状のご所有の賃貸不動産の再生だけではなく、多角的に分析し、今後の賃貸経営のあり方を含めてご相談をお受けしております。 以上