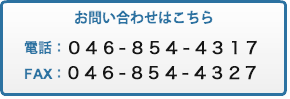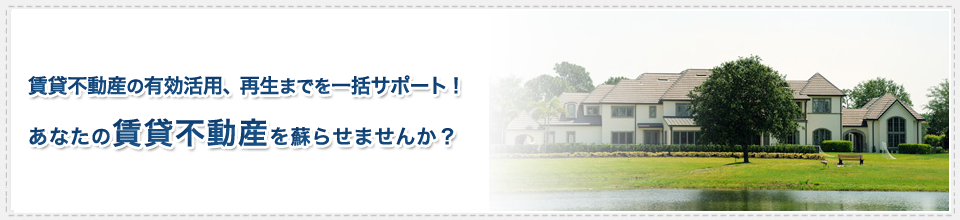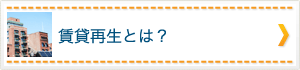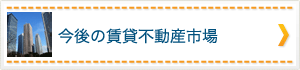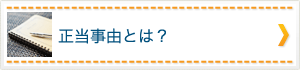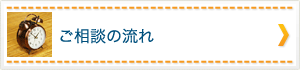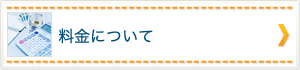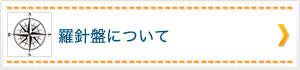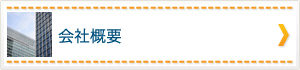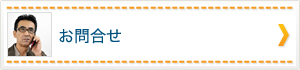「公示地価」は成績表
3月18日国土交通省発表の今年度「公示地価」によれば、東京都23区の商業地、住宅地ともに対前年比で其々3.4%、1.9%上昇とのことです。同様に、横浜市では、商業地が2.4%住宅地が.1.5%の上昇となっております。概ね、地価上昇は、安定的に推移していると思われますが、やはり人口減少の続く地域では、その上昇率は低く、地価の格差となってきております。横浜市でも、南部の金沢・磯子・保土ヶ谷の各区の住宅地の上昇率は1%以下となっております。因みに、人口減少が続く、横浜市に隣接する横須賀市の地価は、商業地で▲0.9、住宅地で▲1.4%なっております。
地価は、様々な要因によって形成されておりますが、結局、「住みやすさ」や「利便性」等を総合的に判断され、需要と供給のバランスにより、市場で形成されるものと思われます。しかし、これは、行政や住民の力によっても変化することも忘れてはならないのも、また事実です。日経ネット3/26によれば、名古屋市に隣接する愛知県長久手市(人口5万4千人)が「住みやすさ」「子育てがしやすい」等の各種調査で日本一になったとのことでございます。そこでは、行政と地域住民がともに支え合い連携して、都市を形成していく姿勢が感じられます。そして、長久手市の住宅地の地価は、前年比3.3%の上昇となっております。
この事実から考えさせられるのは、人口減少社会の中での都市の優劣は、その立地条件だけではなく、行政と住民が如何に支え合う組織を作り、住民参加型都市をいち早く形成したところが、生き残っていくという至極当然な結果です。地価もまた、それを反映していくという事実です。ある意味、地価は、行政やその住民に対する成績表の一つとして考えることもできるのではないでしょうか。 以上