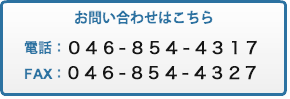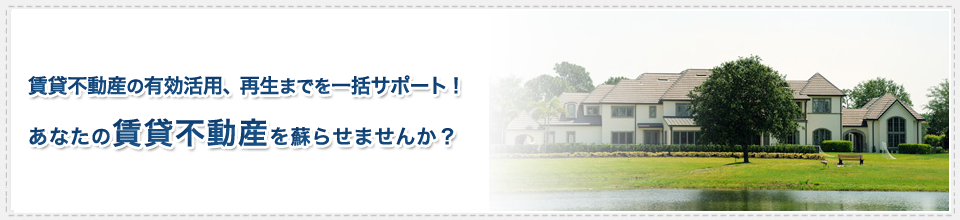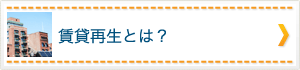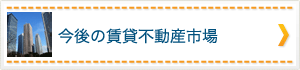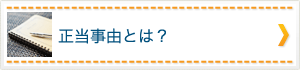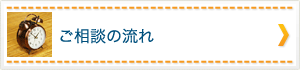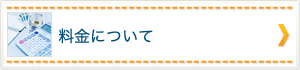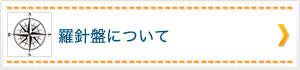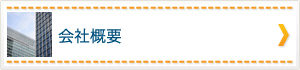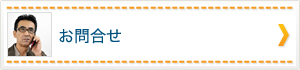「新しい共生社会」とボランティアの必然性
7月26日 日経朝刊によれば、日本でも経済特区を利用して外国人のお手伝いさんの導入を図るべく、国内3社に許可が出たとのことであります。当面は、フィリピン人を採用して11月から稼働を予定しているとのことです。高齢者や共稼ぎが増えて家事代行サービスの需要が増加しているのにも関わらず、国内には、その需要に答える人材が供給できないとのことです。従来は、介護士や建設業の型枠工など一部にしか見られなかった外国人労働者への需要が、少子高齢化の進展に伴って他の分野まで及んできているものと考えます。
一方、国の財政は、消費税の増税延期もあり、緊迫度を増しており、今年度末には、国の借金は対GDP比205%の1062兆円とのことです(財務省:HP)
人出不足は深刻さを増し、財政はいよいよ厳しい中で、国民の行政に対する要望は留まることはなく、今後、行政の人出不足も顕著になってくるものと思われます。この様なギャップを埋める手段として、女性の活用はもちろんですが、高齢者のボランティアとしての活躍もまた望まれているのではないでしょうか。一般に、ボランティアというと、高齢者施設のお手伝いや災害のあと片づけるをイメージしますが、ここでは、あらゆる職種のボランティアが必要とされると思います。
例えば、民間企業で総務関係の仕事を長年やられてきた方には、福祉関係の補助金交付先の組織の再構築に力を貸してもらい補助金の削減を図るとか、民間の金融関係で不良債権を扱ってきた方には、様々な補助金交付先への不良債権の回収に当たっていただくとか、従来では考えられなかった分野への活躍が期待されるのではないでしょうか。
高齢者側も、健康と気力が許す限り、生涯現役を目指して、新しい共生社会の担い手として社会貢献することが求められている自覚を持つべきではないでしょうか。
他方、行政側も、限られた予算を有効に使うため、従来からの秘密主義を改め広く住民に協力を依頼し、住民とともに「新しい共生社会」の構築を求めていくことが、今、最も求められているのではないでしょうか。 以上