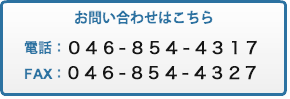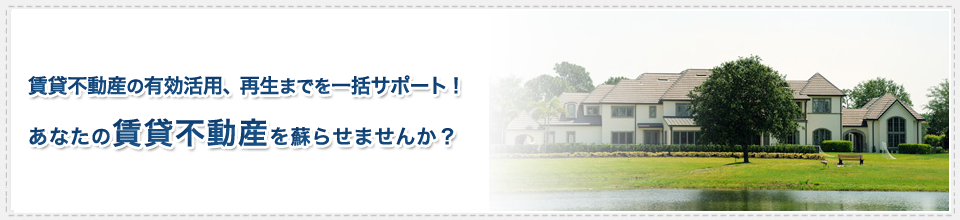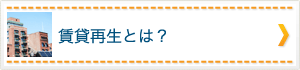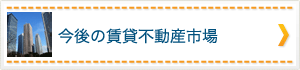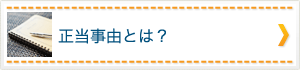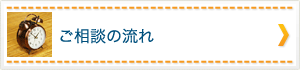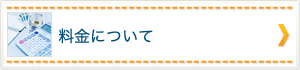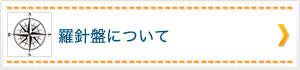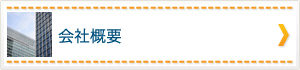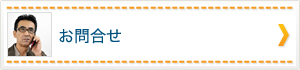先送りは許されない「人口減少対策」
5月17日に、大阪市で行われた住民投票の結果、大阪市民は、従来の行政組織の踏襲による将来を選択されました。従来の様々な問題を解決するための二重行政の廃止が大きな争点でした。
各種報道によれば、50歳代以下の市民では、都構想に対する賛成が多く、70歳以上の高齢層では、反対が多かったとのことでした。事の是非は、当事者である市民に任せるとして、ここで私が懸念するのは、有効投票の中身と年代別投票率です。現在の少子高齢化社会では、有効投票の内、高齢者が占める割合が高く、このため高齢者の意見が多く取り上げられてしまうことです。即ち、今回の住民投票でも、年代層による意見の違いは、明白であり、最も心配していた世代間の闘争となってしまったことです。
社会保障・人口問題研究所の将来人口予想によれば、若年層(20歳~39歳)の減少率は2011年から2020年までの10年間が、将来の期間より、もっとも多い結果となっております。これは、都心を含む全国的な傾向で、どの都市も、政策の現状維持では、将来の展望が開けないのが現状です。
若年層から高齢者までが、バランスよい人口構成が求められますが、高齢者優先の施策では、地域のコミュニティの維持もままなりませし、若年層の鬱積は積るばかりです。そして、若年層の不満は、住居の移転を伴い、担税力のある若年層の流失へと繋がります。
そして、気がつたら、高齢者だけの地域となり、コミュニティは成り立たず、都市としての衰退へと繋がっていくのではないでしょうか。ですので、高齢者の方方にも、将来を見据えた判断をお願いしたいと思います。
この欄でも、何度も取り上げてまいりましたが、今後、賃貸住宅経営においては、その都市の施策が、若年層を取り込めるかが大きなポイントの一つとなるものと思います。何故なら、愛知県の長久手市の様に、行政の施策で人口が増加している都市あるからです。
都市の盛衰は、直接賃貸住宅空室率につながります。賃貸経営者も各都市の施策の違いについて目を凝らして、見ていく必要があるのではないでしょうか。